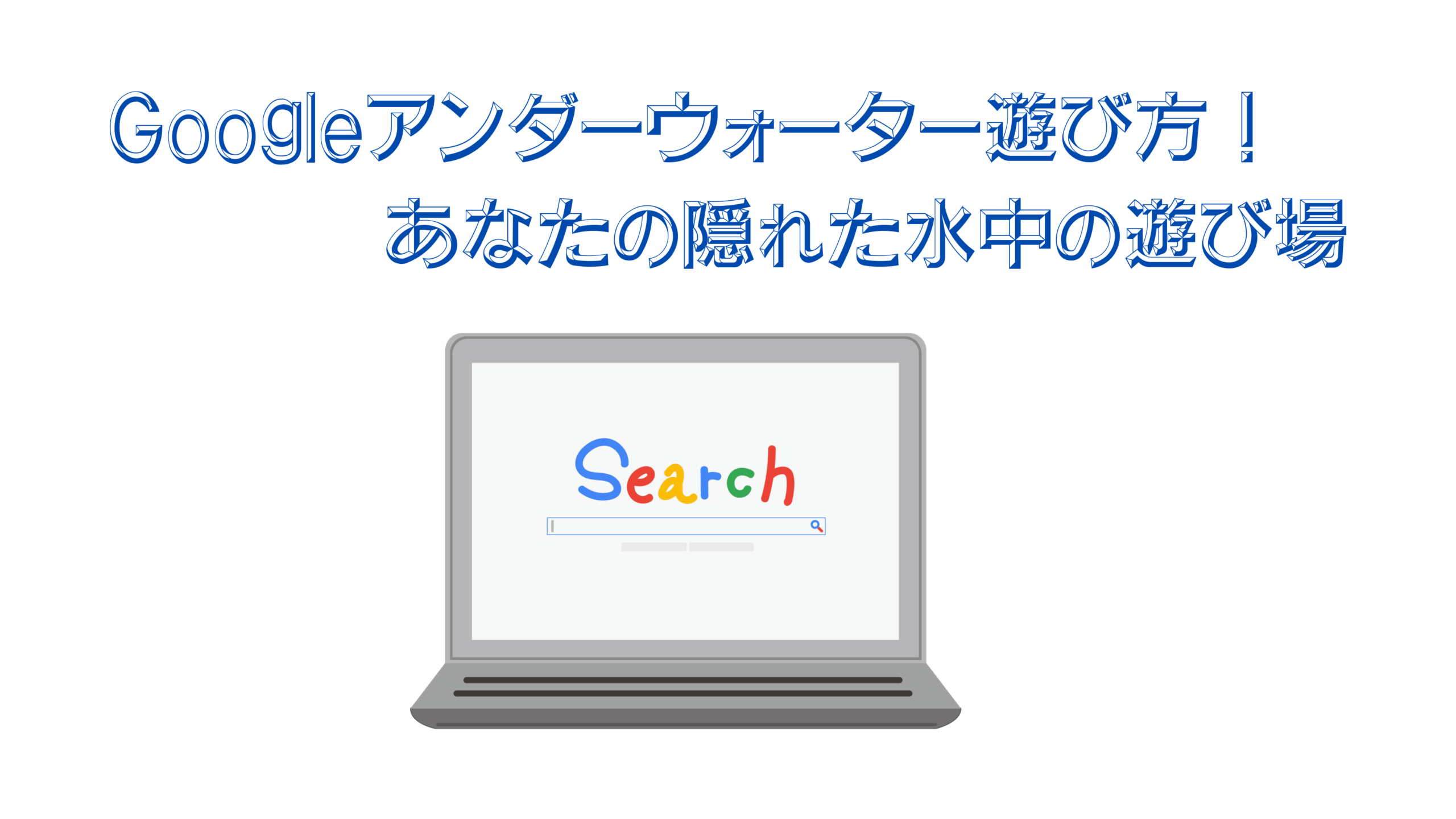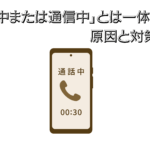Googleには、検索エンジンとしての役割だけでなく、ユーザーを楽しませるための驚きの「隠し機能」やイースターエッグが数多く存在します。その中でもひときわユニークなのが「Googleアンダーウォーター」。この仕掛けは、検索画面全体がまるで水中に沈んでいくようなアニメーション演出が施され、Googleのトップページがまるで巨大な水槽に変身したかのような印象を受ける、視覚的にもインパクトの強いコンテンツです。
この機能は見た目のインパクトだけでなく、検索バーやボタンがゆっくりと浮かび上がったり沈んだりする動きの中で、インタラクティブな遊び心も加えられており、操作しているだけでも楽しい体験が得られます。また、教育やコミュニケーション、SNS発信の話題づくりにも活用されており、年齢を問わず多くのユーザーに人気です。
本記事では、この「Googleアンダーウォーター」の基本的な仕組みやアクセス方法、使い方、他の隠し機能との連携の楽しみ方までを徹底解説。さらに、検索体験を彩る応用的な活用法についても紹介しながら、SEOにも強く、読者に役立つ情報を余すことなくお届けします。
Googleアンダーウォーターとは?

Googleアンダーウォーターの基本解説
Googleアンダーウォーターとは、Googleの公式サービスではないものの、世界中のユーザーに人気の“イースターエッグ”的コンテンツのひとつです。体験できるのは、elgoog.imというミラーサイト。検索エンジンの画面が水に沈み、検索バーやボタンがゆっくりと水面に浮かぶという斬新なアニメーションが特徴です。シンプルながらも、視覚的に強いインパクトを与える仕掛けが満載で、初めて見た人には驚きを与え、話題性も抜群です。
また、サイトの設計はHTMLとJavaScriptを駆使して作られており、ブラウザ上で動作するため、特別なアプリのインストールや設定は不要。スマートフォンやPC、タブレットなど、どの端末でも簡単にアクセスできるという利便性も、この機能の魅力の一つです。
グーグル水中の遊び場としての魅力
この機能の真の魅力は、単なる遊びにとどまらない「多用途性」にあります。教育現場では、授業のアイスブレイクとして活用されたり、プレゼンテーションやイベントの演出に使われることも。水中で漂う検索バーやロゴの動きは、まるでインタラクティブなアート作品のようで、大人から子どもまで誰もが楽しめます。
さらに、YouTube動画やSNSでのショートコンテンツ作りにも相性抜群。特にTikTokやInstagramのリールなどでは、視覚的にユニークな演出が再生数の向上につながるため、Googleアンダーウォーターを素材にした投稿が人気を集めています。癒し系コンテンツとしても需要があり、見ているだけでリラックスできるという声も少なくありません。
グーグル無重力の体験
Googleアンダーウォーターの特徴的なエフェクトの一つが「無重力感」です。画面上のテキストやボタンが水に浮かぶようにふわふわと動く様子は、まるで宇宙空間に放り出されたような錯覚すら覚えます。この演出により、通常の検索画面とは一線を画す没入感があり、好奇心をかき立てられます。
また、ユーザーがマウスを動かしたり、タップしたりすることで、画面上に波紋が広がるなど、インタラクションによって反応する要素も多く、まるで自分が水中にいるかのような感覚を体験できます。単なる視覚的演出にとどまらず、触って楽しめる仕様になっているのが、多くの人に支持される理由の一つです。
アンダーウォーターの遊び方

underwater機能の使い方
Googleアンダーウォーターを使うには、まず「elgoog underwater」または「Google Underwater」と検索します。検索結果に表示されるelgoog.imの専用ページにアクセスすると、Google検索ページそっくりの画面が現れます。その画面では、数秒後に突然水が流れ込み、検索バー、ロゴ、検索ボタンが水中に浮かぶように動き始めます。この演出が始まると、まるで自分のブラウザが水槽になったかのような不思議な感覚に包まれます。
さらに、このサイトはHTML5とJavaScriptによって構成されているため、インストール不要で手軽に楽しめます。パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットからでも快適にアクセスできるのが特徴です。職場のちょっとした息抜きや、プレゼンの小ネタとしても使えるので、思わぬシーンで役立つ可能性があります。
水に浮かぶ体験をする方法
水中に沈んだ検索バーやボタンは、実際にクリックしたりドラッグしたりすることができます。マウスや指でアイコンを触ると、ゆっくりと流れたり跳ねたりしながら、水中を浮遊する動きを見せます。検索結果を表示するという機能自体はそのまま使えるため、「Googleの別の顔」として遊びながら情報検索ができるのも魅力のひとつです。
また、波紋が広がるアニメーションや、複数のオブジェクトが水面でぶつかる表現など、細部にわたる動きも丁寧に再現されています。複数人で画面を見ながら楽しめるような工夫もされており、まるで水中でインタラクティブなゲームをしているかのような感覚も味わえます。スクリーンキャプチャや録画ツールを併用することで、オリジナルの水中ムービーを作成することも可能です。
googleミラーとの連携
elgoogは“Google Mirror”とも呼ばれ、Googleのさまざまな隠し機能を再現したパロディ的コンテンツを提供しています。その中でもアンダーウォーターは特に人気の高い機能で、Google Gravity(重力で要素が落ちる機能)やGoogle Space(無重力空間で文字が動く機能)などと並び、視覚と操作性の両方で楽しませてくれるのが特徴です。
連携のコツとしては、ブラウザのタブで複数のミラー機能を同時に立ち上げて切り替えながら遊ぶ方法があります。たとえば、水中の演出を楽しんだあとにGravityで崩壊する検索ページに切り替えるなど、エンターテイメント性を強化する使い方も可能です。こうしたコンテンツを組み合わせて、自分だけのオリジナル「Google演出ショー」を楽しんでみてはいかがでしょうか。
Googleアンダーウォーターの隠れた機能

グーグルグラビティ水中の楽しみ方
Google Gravityと組み合わせることで、水中+重力のユニークなシーンを演出できます。通常は画面上に整列されている文字やアイコンが、重力の作用でバラバラと落下していくのがGoogle Gravityの特徴ですが、アンダーウォーターと併用することで、落ちるはずの要素が水中でふわふわと浮かび上がる、幻想的で不思議な演出が楽しめます。
たとえば、検索バーが水面下に沈んだかと思えば、重力の影響で斜めに回転しながら再浮上するなど、現実にはあり得ないような動きが表現され、見る人に驚きと笑いを与えます。このような視覚効果は、動画コンテンツや教育の中で「現実と仮想の違い」を説明する題材としても活用可能です。PCの画面収録ツールを使えば、このユニークな体験を映像に残して友人と共有することもできます。
elgoogの特別機能
elgoogには、他にも「Google太鼓(Google Drum)」や「Googleスネークゲーム」など、Google本体では味わえない遊び心たっぷりの機能が満載です。これらはただのジョーク機能にとどまらず、ユーザーの操作に対して反応するインタラクティブ性を持ち、見ているだけでなく実際に“遊べる”仕掛けとして高く評価されています。
また、「Google 反転(Google Mirror)」や「Google Terminal」などのユニークな機能もあり、それぞれが独立しても楽しめる構造になっているのが魅力です。これらを順に体験していくことで、まるでGoogleの裏側を探検しているような感覚を味わうことができます。プレゼンのネタにしたり、ブログやSNSの投稿コンテンツとしても活用しやすく、クリエイターにとっても有用なツール群となっています。
重力による新しい体験
Googleの検索画面に重力を与えることで、まるで現実世界に入り込んだかのような物理的リアリティを感じることができます。たとえば、文字が落下して衝突する音や、オブジェクトが跳ね返るアニメーションによって、まるで仮想空間内に重さや抵抗を感じているような不思議な没入感が生まれます。
このような体験にアンダーウォーターの演出を加えることで、画面全体が「水中にあるリアルな空間」として再構築され、ユーザーはまるでその空間の一部になったかのような感覚を味わえます。子どもたちにとっては学習と遊びの融合、大人にとっては癒しや刺激的なインスピレーション源にもなる、非常に多面的なコンテンツ体験が可能です。
ゲームとアプリのおすすめ

人気の水中ゲーム
水の中を舞台にしたゲームとしては「フィッシュダム」や「Hungry Shark」などが根強い人気を誇ります。「フィッシュダム」はパズルを解いて自分だけの水族館を作れる癒し系のゲームで、美しいアニメーションと穏やかなBGMが特徴です。一方、「Hungry Shark」はスリル満点のアクションゲームで、プレイヤーはサメとなり、海の中で獲物を探して泳ぎ回るという爽快なプレイ感が魅力です。
さらに、最近では「Subnautica」や「ABZÛ」などの水中探検ゲームも注目を集めており、これらは深海の神秘や自然との調和をテーマにした、ストーリー性の高いゲームとして高評価を受けています。Googleアンダーウォーターと視覚体験が似ているため、同じような没入感を求めるユーザーにはぴったりです。
おすすめのアプリ
iOS・Androidの両方に対応している水中テーマのアプリは多数存在します。たとえば、拡張現実(AR)を利用してスマホ越しに海中の世界をリアルに体験できる「Ocean AR」は、子どもたちの教育用ツールとしても評価が高く、家庭や学校でも利用されています。また、「Aquarium Live」や「Relaxing Ocean Sounds」など、視覚と聴覚を同時に癒してくれるアプリもあり、日々のストレス解消や作業用BGMとして活用する人も多いです。
その他、「MyReef 3D」「Fish Farm」などのバーチャルアクアリウムアプリも人気です。ユーザーが自由に魚を育てたり、背景や飾り付けをカスタマイズしたりできる機能があり、単なる観賞用にとどまらず、自分だけの“デジタル水槽”を作る楽しさが味わえます。
アプリの活用法
これらのアプリは、単に遊ぶだけではなく、教育やリラクゼーション、クリエイティブ活動にも応用可能です。たとえば、子ども向けには海の生態系を学ぶ教材として活用でき、大人にとってはマインドフルネスや集中力を高めるツールとしても効果的です。最近ではVRデバイスと組み合わせることで、さらにリアルな仮想水中体験が可能になっており、家庭内でのバーチャル旅行や癒しの空間づくりにも使われています。
Googleアンダーウォーターとこれらのアプリを併用することで、視覚的な連続性やストーリー性のある演出を加えることができます。たとえば、アンダーウォーターで検索した後に「Ocean AR」で深海探検に出かけたり、プレゼンや授業で仮想の水中テーマを演出したりするなど、創造的な活用方法が広がります。
写真撮影とデータの取り扱い
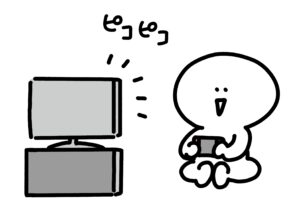
水中撮影のポイント
Googleアンダーウォーターでは、画面キャプチャ機能を活用して「水中に沈んだGoogle検索画面」や、浮遊する検索ボタンの様子などを画像として保存することができます。キャプチャのタイミングによっては、検索ボックスがちょうど沈んでいる瞬間や、波紋が広がっている印象的なシーンを捉えることができ、非常にユニークな画像になります。
SNSへの投稿はもちろん、プレゼン資料やブログ記事の素材としても活用でき、Googleの遊び心を伝えるツールとしても効果的です。また、動画キャプチャを活用すれば、より臨場感のあるアンダーウォーター体験を記録することが可能です。録画後にGIFアニメに変換することで、SNSやチャットアプリでも気軽に共有できます。
撮影データの管理方法
撮影したキャプチャ画像は、GoogleフォトやGoogleドライブにアップロードして整理することで、端末の容量を節約しつつ、複数デバイス間でのアクセスも容易になります。クラウド上で「Google遊び機能」「elgoog」などのラベルを付けて管理すれば、検索もしやすくなります。
スマートフォンユーザーであれば、専用のアルバムを作成して「アンダーウォーター作品集」などと名付けておくのもおすすめです。定期的にフォルダ内を振り返ることで、新しいアイデアや遊び方を思いつくきっかけにもなります。さらに、SNS用・プレゼン用・教育用などの目的別に分類することで、再活用の効率も高まります。
Googleでデータ検索する方法
Google画像検索を使えば、「elgoog underwater gif」「Googleアンダーウォーター キャプチャ」などのキーワードで、過去にシェアされたユニークな画像やアニメーションを簡単に探すことができます。検索ツールの「GIF」フィルターを使えば、動きのある画像だけに絞って表示できるため、インスピレーションを得たいときにも便利です。
また、PinterestやTumblrといったビジュアル重視のSNSでも、「Google Underwater」関連の作品が多数投稿されているため、参考になる事例が豊富に見つかります。自分のキャプチャと比較したり、新たな構図を発見したりする際のヒントにもなるでしょう。
まとめ

Googleアンダーウォーターは、ちょっとした検索の合間や気分転換にぴったりな、誰でも気軽に楽しめる仮想水中空間です。検索バーが水に浮かび、アイコンがゆらゆらと動くユニークな演出は、思わず微笑んでしまうような遊び心に満ちており、Googleのサービスに新しい視点を加えてくれます。
この記事では、基本的な使い方から連携機能、さらにはゲームやアプリ、データの活用方法に至るまで、幅広く紹介しました。特にelgoogの他のコンテンツと組み合わせることで、無重力や重力操作、水中空間といったさまざまなテーマが一体となり、エンタメ性の高い複合体験が可能になります。動画コンテンツの素材や教育・プレゼン用途にも応用でき、個人でもグループでも楽しめるのが特徴です。
デジタルコンテンツとしての面白さだけでなく、リラクゼーション効果や創造的なインスピレーション源としても活用できるGoogleアンダーウォーターは、まさに「知られざる名コンテンツ」と言えるでしょう。今後も新たな使い方や表現を探しながら、あなたならではの遊び方を見つけてみてください。
この記事をきっかけに、ぜひあなたもGoogleの隠れた水中ワールドに足を踏み入れて、その奥深い魅力を体験してみてください。