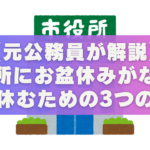「吉」の漢字には、実は2種類あることをご存知ですか?
街で見かける「吉野家」などの看板をよく見ると、下の横棒が長い「よし」が使われていることがあります。
この字は「つちよし」とも呼ばれ、見た目こそ似ていますが、入力方法や公的な扱いには大きな違いがあるんです。
この記事では、「つちよし」の読み方・意味・漢字としての成り立ちから、スマホやパソコンでの変換方法、戸籍で使えるかどうかまで、徹底的に分かりやすく解説します。
環境依存文字の仕組みや、なぜ文字化けが起こるのかといった技術的な背景も紹介するので、「どうして出せないの?」という疑問もスッキリ解消!
名前や屋号などで「つちよし」を正しく使いたい人のために、実用的な対処法も網羅しています。
「つちよし」のモヤモヤをここで一気に解決しましょう。
よしの漢字、下が長いのはなに?基本と違いをわかりやすく整理

「吉」という漢字、よく見ると微妙に形が違う2つのバージョンがあることをご存知ですか?
一見そっくりですが、実は使われ方や意味合いに少し違いがあるんです。
「吉」と「つちよし」の見た目はどこが違う?
まずは見た目の違いを確認してみましょう。
一般的に使われる「吉」は、下の横棒が短いのが特徴です。
一方で「つちよし」と呼ばれるバージョンは、下の横棒が長くなっています。
これは、書き方の癖や印刷上のバリエーションではなく、実際に異なる字として扱われる漢字なんです。
| 表記 | 特徴 | 名称 |
|---|---|---|
| 吉 | 下の横棒が短い | さむらいよし(標準字体) |
| 𠮷 | 下の横棒が長い | つちよし(異体字) |
街中の看板などで目にする場合、「吉野家」や「吉兆」などの屋号には下が長いバージョンがよく使われています。
「士」と「土」の違いが意味するものとは?
さらに詳しく見ると、「吉」の上部の形が「士」(さむらい)であるのに対し、「つちよし」の場合は「土」になっています。
この違いは装飾の違いではなく、漢字の成り立ちに由来しています。
「士」は刃物、「土」は土地や大地を表す象形文字が元となっているため、それぞれに含まれるイメージも異なるのです。
ただし、意味や読み方はどちらも「吉(よし)」とされ、熟語などでも区別されることはあまりありません。
違いがあるとすれば、使われる場面や文字コード上での扱い、それに伴う変換方法の違いです。
つちよしはどう読む?正式名称と意外な読み方

「下が長い吉」こと「つちよし」は、見た目は分かっても正式な呼び方や意味については知らない人も多いですよね。
ここでは「つちよし」の読み方の由来や、「さむらいよし」との呼び分けについて詳しく解説していきます。
「つちよし」って本当にそう読むの?
まず「つちよし」という読み方ですが、これは正式な読みというより、見た目による俗称です。
上部が「土」に見えるから「つち」、そして下が「吉」だから「よし」と呼ばれるようになりました。
一方で、標準的な「吉」は上部が「士(さむらい)」に見えるため「さむらいよし」と呼ばれることもあります。
つまりこの2つの呼び方は、文字そのものの違いを説明するための通称なんですね。
| 通称 | 見た目の構成 | 備考 |
|---|---|---|
| つちよし | 「土」+「口」 | 異体字(𠮷) |
| さむらいよし | 「士」+「口」 | 常用漢字(吉) |
こういった区別は、漢字辞典や日本語の研究ではしばしば取り上げられています。
ただしどちらも読み方は「よし」で共通なので、日常会話では意識する必要はあまりありません。
「士よし」との呼び分け・由来とは?
実際に公的な文書や名前の登録などで区別されることはほとんどなく、環境によって自動的に「つちよし」に置き換えられることもあります。
これは、コンピュータが表示できる文字に制限があるためで、後ほど解説する「環境依存文字」に関わる問題です。
とはいえ、屋号や人名などで明確に「つちよし」を使いたい場合もあるため、この読み分けや意味の違いを知っておくと便利です。
次の章では、実際に「つちよし」をスマホやパソコンで出す方法を、画像付きで詳しくご紹介していきます。
つちよしはスマホ・PCで出せる?実際の変換手順ガイド

「つちよし」の漢字を使いたいけど、スマホやパソコンでうまく変換できない…そんな経験ありませんか?
実はこの漢字、環境によっては入力方法がちょっと特殊なんです。
ここでは、各デバイスごとの出し方と注意点をわかりやすく解説します。
Windows/Macでの出し方と環境依存の注意点
WindowsやMacなどのPCでは、「よし」と入力して変換すれば「𠮷(つちよし)」が候補に出てくる場合があります。
しかし、出てこない場合も多いんです。
その場合は以下の方法を試してみましょう。
- ネット上で「𠮷」をコピーして、そのまま貼り付ける
- IMEパッド(Windows)から「単語登録」を使って登録する
- Macでは「文字ビューア」で該当の字を検索し、コピー&ペースト
また、「𠮷」はJIS2004以降で収録された文字なので、古いOSや古いソフトだと文字化けすることもあります。
| OSバージョン | 変換できる? | 対応策 |
|---|---|---|
| Windows 10以降 | 〇 | 変換候補に出る or 単語登録 |
| Windows 7以前 | △ | 文字化けの可能性あり、要コピペ |
| Mac(Ventura以降) | 〇 | 文字ビューア使用 |
一番確実なのは、コピー&ペースト+単語登録です。
iPhone/Androidでの出し方と辞書登録方法
スマホで「𠮷」を出すのは、PCよりも少し手間がかかります。
iPhoneやAndroidでは通常「よし」と入力しても変換候補に出てこないことが多いからです。
その場合は「ユーザー辞書」に登録する方法が有効です。
- ネットなどで「𠮷」をコピー
- スマホの設定 → 一般(Androidでは「システム」) → キーボード → ユーザー辞書
- 「単語」に𠮷をペースト、「読み」に「よし」や「つちよし」を入力
これで次回以降、「よし」と打つと変換候補に出るようになります。
機種やOSによって出ない時の対処法まとめ
機種によっては、そもそも「𠮷」が表示されなかったり、変な記号になる場合もあります。
このようなときは次のように対処しましょう。
- 最新のOSにアップデートする
- 文字を画像化して送る(メールや名刺などでどうしても必要な場合)
- 正式文書では「吉」に統一してもらう
特に公的な書類では、「𠮷」が登録できない場合もあるので注意が必要です。
つちよしはなぜ変換できない?環境依存文字の仕組みと課題

「つちよし」が変換できなかったり文字化けするのは、なぜなのでしょうか?
そのカギを握っているのが「環境依存文字」という存在です。
この章では、その仕組みと現状の課題をわかりやすく解説します。
環境依存文字とは何か?JISコードと文字化けの問題
環境依存文字とは、「特定の機種やOSでしか表示できない文字」のことを指します。
たとえば、「髙」「㋿」「㎥」などが有名ですね。
この原因は、パソコンなどで扱う文字コード(JISコードやUnicode)が関係しています。
文字にはそれぞれ番号(コード)が振られていて、それに対応するフォントが存在しないと、「?」や「□」に置き換わってしまうのです。
| 文字 | 対応OS | 対応フォント |
|---|---|---|
| 𠮷 | Windows 10以降、iOS13以降 | Yu Gothic、游明朝など |
| 髙 | ほぼすべてのOS | MS明朝、Yu Gothicなど |
| ㋿ | 一部旧OSでは非対応 | 対応フォントのみ表示可 |
つまり、「𠮷」が変換できないのは、その字を表示するための番号やフォントが、あなたの端末にないからなんです。
「ヴ」や「髙」など、他の環境依存文字と同じなのか?
「つちよし」だけが特別というわけではありません。
たとえば「ヴ」も昔はカタカナとして扱えず、「ゔ」も平仮名で変換できない機種がありました。
「髙」も高の異体字ですが、使用者の名前に使われている場合、同じような変換・表示のトラブルがあります。
これらに共通するのは、どの文字コード規格に登録されているか、使用するフォントが対応しているかという点です。
今後はUnicodeの普及とともに改善が進んでいますが、完全に解決されるにはもう少し時間がかかりそうです。
つちよしはなぜ存在する?漢字の成り立ちと歴史を深掘り

「𠮷(つちよし)」という漢字がなぜ存在するのか、疑問に思ったことはありませんか?
ここでは「吉」と「𠮷」の成り立ちや意味の違い、なぜ2種類あるのかという歴史的な背景を紹介します。
古代中国の象形文字から見る「吉」の起源
「吉」という字のルーツは、古代中国の殷王朝時代にまで遡ります。
当時使われていた「甲骨文字」では、「士(武器の象形)」と「口(祈りの言葉の象形)」を組み合わせた形が「吉」でした。
「おめでたい言葉を祈る儀式」を意味していたとされ、そこから「めでたい」「良い」といった意味に発展していきました。
この時点での形は、「士(さむらい)」+「口」が基本。
つまり現代でいう「さむらいよし」が、本来の姿だったわけです。
「つちよし」は旧字?異体字?正式な使い方とは
「𠮷」は、「吉」の旧字だと誤解されることがありますが、実は旧字ではなく“異体字”です。
異体字とは、意味や読みは同じで、字体(見た目)が違う漢字のこと。
例えば以下のような例があります:
| 異体字 | 標準字体 | 意味の違い |
|---|---|---|
| 澤 | 沢 | 意味は同じ、水辺 |
| 龍 | 竜 | 意味は同じ、伝説の生物 |
| 𠮷 | 吉 | 意味は同じ、めでたい |
つまり、「𠮷(つちよし)」は単なる字形のバリエーションであり、正式な「吉」のバージョンではありません。
戦前や戦後すぐの印刷文化のなかで、デザイン上の都合で「𠮷」が使われたと考えられています。
現在ではJIS規格などでも区別され、環境によって表示の可否が異なる文字となっています。
つちよしは公的文書や戸籍に使える?法的な扱いと注意点

では、「𠮷(つちよし)」は戸籍や公的文書に正式に使えるのでしょうか?
ここではその法的な扱いと注意点を詳しく見ていきましょう。
現在の戸籍法で認められているのはどっち?
結論から言えば、戸籍法上、認められているのは「吉」のみです。
「𠮷」は異体字にあたるため、戸籍や住民票、パスポートなどの公的書類では基本的に使用できません。
これは、昭和22年に制定された「当用漢字表(現在の常用漢字)」によって、戸籍で使用できる漢字が制限されたことが背景にあります。
その後も「𠮷」は人名用漢字として追加されることはなく、あくまで「吉」のみが標準として使われています。
つまり、名前に「𠮷」が含まれていても、役所などでは「吉」に修正される場合があります。
ただし、以前から登録されていた場合はそのまま継続使用されるケースもあります。
人名用漢字・異体字の採用ルールとその背景
日本では、人名に使用できる漢字は「常用漢字」と「人名用漢字」に限定されています。
「𠮷」は、JIS X 0213のレベル2に含まれているにもかかわらず、人名用漢字としては採用されていません。
その理由としては以下のような点が挙げられます。
- フォントやソフトによって表示できない環境がある
- 正式な読み・書きが曖昧で、行政上の統一が困難
- 手続きミスや文字化けなどのトラブルリスク
このような事情から、いくら「つちよし」を使いたいと思っても、法的・技術的に制限があることは理解しておく必要があります。
次の章では、そんな中でも「𠮷」をあえて使い続けている企業や人物に焦点を当て、その理由を探っていきます。
つちよしが今も使われる理由と文化的な背景

公的な文書では使えないとされている「つちよし」ですが、それでも今も目にする機会は意外と多いですよね。
実はこの漢字、特定の場面や業界ではあえて「つちよし」を使い続けているところがあるんです。
ここではその背景や理由を、具体的な事例とともに紹介します。
「吉野家」や「吉兆」があえて使っている理由とは?
まず代表的なのが、「吉野家」や「吉兆」といった老舗企業です。
どちらも社名の「吉」が、下の棒が長い「𠮷」になっています。
これは単なるデザインではなく、創業当時からの正式な表記です。
理由としては:
- 創業者の名前に「𠮷」が使われていた
- 縁起の良さや印象を重視したロゴデザイン
- 伝統・格式を感じさせる表現としてのこだわり
特に「吉兆」は、京都発祥の日本料理の老舗として、格式や伝統を大切にしてきた背景があります。
このような場では、漢字の持つイメージや文化的な重みが大事にされているんですね。
吉田茂総理の名前が切り替わった歴史的背景
もうひとつ興味深い例が、戦後の首相・吉田茂さんです。
戦前までは「𠮷田茂」と表記されていましたが、昭和24年、政府の公式文書で「吉田茂」に統一されました。
これは「当用漢字表」に基づく国語改革の一環です。
当時の事情を振り返ると、次のような背景がありました。
- 戦後の文書簡略化・印刷技術の統一
- 国民の識字率向上と教育標準化
- 公的記録での誤記・混乱を避ける目的
つまり「𠮷」は伝統的で格式ある文字と見なされる一方、行政・教育の現場では扱いにくいと判断されたわけです。
それでも、今もこの字を好んで使う人たちがいるのは、文化的な価値が評価されているからと言えるでしょう。
つちよしは今後どうなる?今後のデジタル対応の行方

「つちよし」は使いたくても文字化けや入力できない問題がつきまといます。
では、この先はどうなるのでしょうか?
技術と制度の面から、今後の対応について考えてみましょう。
JISコードやUnicodeの進化と今後の可能性
現在、多くの文字はUnicode(ユニコード)という世界共通の文字コードに統一されています。
「𠮷」もUnicodeではU+20BB7として登録済みです。
つまり、技術的には「つちよし」を扱える準備はできているということなんですね。
一方でJIS(日本工業規格)では、文字の使用状況やニーズに応じてバージョンアップが進められています。
2004年のJIS改訂(JIS X 0213)では「𠮷」も正式に採用されており、今後はデジタルフォントやOSアップデートの普及で徐々に使いやすくなっていく可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| Unicodeコード | U+20BB7 |
| JIS規格採用 | JIS X 0213:2004以降 |
| 今後の展望 | フォント・OS側での対応次第で普及拡大 |
フォントや表示環境でできる対処法まとめ
「𠮷」が表示できるかどうかは、実はフォントにも大きく左右されます。
次のようなフォントでは、対応している可能性が高いです。
- 游明朝 / 游ゴシック
- Yu Gothic UI
- 源ノ明朝 / 源ノ角ゴシック(Google提供)
逆に、古いバージョンのMS明朝やMSゴシックでは、文字化けのリスクが高いです。
どうしても表示させたい場合は:
- 対象フォントをインストールする
- 画像化して貼り付ける
- HTMLやPDFなどで文字埋め込みを行う
「使いたい」と「読ませたい」を両立する工夫が求められますね。
次章では、ここまでの話をまとめつつ、「つちよし」を上手に扱うためのポイントを振り返ります。
まとめ|つちよしは特殊だけど意味がある。正しく使いこなそう

ここまで「つちよし(𠮷)」の出し方、使い方、歴史、技術的背景について見てきました。
最後に大切なポイントをまとめつつ、「つちよし」とうまく付き合っていくためのヒントを整理しておきましょう。
覚えておきたい「つちよし」のポイント
まずは記事全体の要点をコンパクトにおさらいします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 見た目の違い | 「吉」…下の横棒が短い、「𠮷」…下が長い(「土」に見える) |
| 分類 | 「𠮷」は「吉」の異体字(意味・読みは同じ) |
| 入力方法 | PC・スマホともに「辞書登録」が確実/表示は環境依存 |
| 公的利用 | 戸籍などでは「吉」のみ使用可、「𠮷」は非対応が多い |
| 技術的背景 | Unicodeには登録済み(U+20BB7)、JIS規格でも採用済 |
「つちよし」は正しい知識があれば使いこなせる漢字です。
ただし、使用する場面や相手の環境によっては慎重になる必要もあります。
どうしても出したいときの最終手段
もしも「どうしてもつちよしを使いたい!でも環境が古くて無理!」という場合、以下の方法が役に立ちます。
- 画像として貼り付ける:ロゴや名刺、年賀状などで視覚的に使いたい場合に有効
- フォントを埋め込んだPDFで送る:文字化け防止に有効
- 注釈をつけて併記する:(例:「𠮷(つちよし)」と明記)
特にビジネスや公的な文書では、誤解やトラブルを避けるための配慮が重要になります。
このように、「つちよし」はやや扱いにくい一面があるものの、名前や文化を大切にしたい人にとっては、思い入れのある漢字でもあります。
正しい知識を持って、スマートに、そして大切に使っていきたいですね。