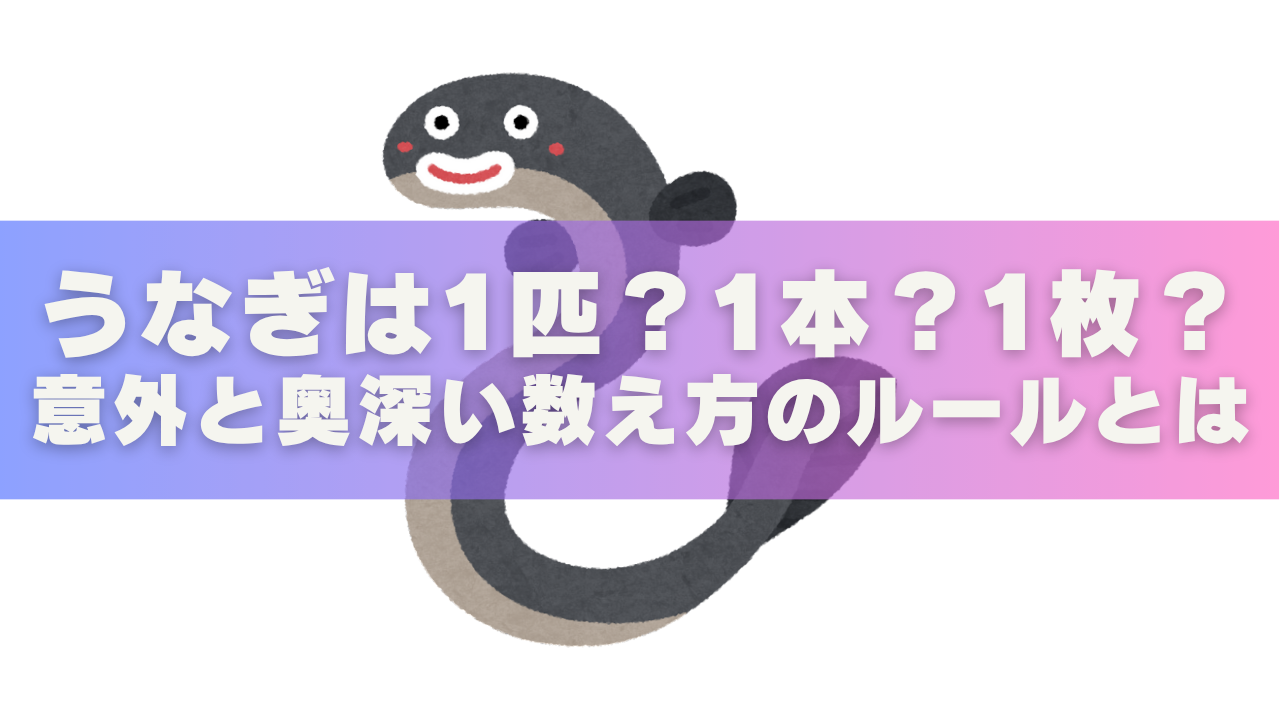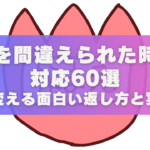「うなぎって、どうやって数えるの?」そんな素朴な疑問を持ったこと、ありませんか?
実はうなぎの数え方は、その状態によって変わるんです。
生きているときは「匹」、食材になれば「尾」や「本」、蒲焼きにされれば「枚」や「串」など、意外と複雑なルールがあるんですよ。
本記事では、うなぎの状態別・料理別の正しい数え方をわかりやすく解説。
さらに、「なぜ蒲焼って呼ぶの?」という語源の話や、知識として知っておくと食事がもっと楽しくなる豆知識までご紹介します。
この記事を読めば、あなたも今日から“うなぎ通”。
ぜひ最後までお楽しみください。
うなぎの数え方は「状態」で変わる?

「うなぎって、どう数えるの?」と聞かれたとき、実はその答えはひとつではありません。
うなぎは、生きているか、調理されているか、焼かれているかによって、使う数え方が変わってくるのです。
この章では、うなぎの状態ごとにどんな数え方をするのかを、わかりやすく整理していきます。
生きているうなぎの数え方は?
まず、生きているうなぎの場合は「匹(ぴき)」で数えます。
これは、犬や猫と同じで、小型の動物に使う一般的な数え方ですね。
「頭(とう)」という単位もありますが、これは牛や馬など、大型の動物に使われるのが一般的です。
したがって、うなぎを生きたまま桶に入れている場面では、「3匹のうなぎ」などと言うのが自然です。
| 状態 | 数え方 | 例文 |
|---|---|---|
| 生きている | 匹(ぴき) | うなぎが5匹泳いでいる |
調理されたうなぎの数え方は?
うなぎが調理のためにさばかれて、食材として扱われるようになると、「尾(び)」や「本(ほん)」と数えます。
この「尾」は、魚やうなぎなどの細長い形状のものに使われる伝統的な数え方。
「本」は、比較的カジュアルに使われることが多く、スーパーや料理店でもよく見かけます。
| 状態 | 数え方 | 例文 |
|---|---|---|
| 調理前の食材 | 尾(び)・本(ほん) | うなぎを2本買って帰る |
蒲焼きになったうなぎの数え方は?
蒲焼きや白焼きなど、焼き上がった料理としてのうなぎは、「枚(まい)」や「串(くし)」で数えます。
「枚」は、薄く平らなものに使われる数え方で、お弁当などでは「うなぎの蒲焼1枚」などと書かれることが多いです。
「串」は、うなぎを串に刺して焼いた場合に使われます。うなぎ屋ではこちらの方が一般的ですね。
| 状態 | 数え方 | 例文 |
|---|---|---|
| 蒲焼・白焼き | 枚(まい)・串(くし) | 蒲焼を2枚注文する |
うなぎの数え方は、状態によって「匹」「尾」「枚」などに変化します。
うなぎ料理別の数え方もチェックしよう

うなぎは蒲焼きだけではありませんよね。う巻きや肝など、いろいろな料理に姿を変えます。
その料理の種類によっても、適切な数え方があるんです。
この章では、代表的なうなぎ料理ごとの数え方をご紹介します。
う巻きの数え方は?
う巻きは、だし巻き卵の中にうなぎを巻いた料理ですね。
このう巻きを丸ごと一本出す場合は「本」で数えます。
しかし、切り分けられた状態で提供される場合は「個」として数えるのが一般的です。
| 料理 | 数え方 | 例文 |
|---|---|---|
| う巻き(丸ごと) | 本(ほん) | う巻きを1本ください |
| う巻き(カット済み) | 個(こ) | う巻きを3個に切ってある |
うなぎの肝はどう数える?
うなぎの肝(きも)も、栄養が豊富で人気の食材です。
この肝は、一般的には「個」で数えられますが、料理店によっては「串」で出されることもあります。
たとえば、肝串焼きのような場合ですね。
| 料理 | 数え方 | 例文 |
|---|---|---|
| 肝(単体) | 個(こ) | うなぎの肝を2個もらう |
| 肝串 | 串(くし) | 肝串を3串注文する |
料理に応じて「本」「個」「串」などの数え方を使い分けると、食通っぽくてスマートです。
なぜ「蒲焼」という名前になったの?
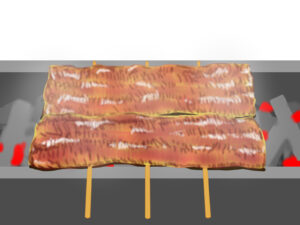
ところで、うなぎを焼いた料理がなぜ「蒲焼(かばやき)」と呼ばれるようになったのか、気になったことはありませんか?
この章では、ちょっとした雑学として、蒲焼という名前の由来について解説していきます。
蒲の穂に似ていたという説
もっとも有名な説が、「蒲(がま)の穂に似ているから」というものです。
昔の蒲焼は、うなぎを縦に串に刺して焼いていたため、焼き上がった形が植物の「蒲の穂(がまのほ)」に似ていたといわれています。
蒲の穂は、棒のように細長く茶色い形をしていて、確かに昔の串焼きうなぎと雰囲気が似ているんですよね。
| 名称 | 由来 | 特徴 |
|---|---|---|
| 蒲焼 | 蒲の穂に似ていた | 細長くて茶色い形状 |
他にもある?名前の由来説
一方で、他にもいくつかの説があります。
たとえば「かばね焼き(屍焼き)」が転じて「かばやき」になったという、ちょっと怖い説も。
これは、開いたうなぎの形が人の体に似ているから…という説ですが、信憑性はやや低めです。
また、焼いたときの香りが「香ばしい=かばやしい」と言われたという説もあります。
| 説の名前 | 概要 | 信憑性 |
|---|---|---|
| 蒲の穂説 | 串に刺した形が蒲の穂に似ている | 高い |
| かばね焼き説 | 形が人の体に似ていた | やや低め |
| 香ばしい説 | 焼いた香りに由来 | 中程度 |
一般的には「蒲の穂に似ていた」という説が最も有力とされています。
数え方を知れば、うなぎがもっと美味しくなる

ここまでで、うなぎの状態別・料理別の数え方を学んできましたが、実はこの知識がうなぎをさらに美味しく感じさせてくれるんです。
この章では、その理由と活用法を見ていきましょう。
知識が味を深める理由
料理を食べるとき、その背景を知っていると味わいも深まりますよね。
たとえば、蒲焼1枚に込められた調理の手間や、素材の希少さを知っていると、「ありがたみ」が変わってきます。
また、正しい数え方を知っていると、お店での会話やオーダー時にもスマートに振る舞えます。
| 知識 | 得られるメリット |
|---|---|
| うなぎの数え方 | お店での注文がスムーズになる |
| 由来や背景 | 食事に対する理解と満足感がアップ |
お店でも使える!正しい言い方
たとえば、うなぎ料理専門店で「蒲焼き1枚ください」と言えば、きちんと理解されます。
一方で「うなぎ1匹ください」と言うと、生きたうなぎを想像されてしまうかもしれません。
また、お土産用のうなぎを買うときは「2本ください」などと伝えると、店員さんもわかりやすく対応できます。
うなぎの数え方を知っていると、食事の場がもっと豊かで楽しい時間になります。
まとめ

ここまで、うなぎの数え方について、生きている状態から蒲焼になった後まで、詳しく見てきました。
最後に、この情報をもう一度整理して、しっかり記憶に残せるようにまとめておきましょう。
うなぎの状態別の数え方
まず、うなぎはその「状態」によって使う数え方が異なります。
これは日本語の面白さの一つであり、また料理文化の奥深さを感じられるポイントでもあります。
| うなぎの状態 | 使われる数え方 |
|---|---|
| 生きている | 匹(ぴき) |
| 調理された食材 | 尾(び)・本(ほん) |
| 蒲焼・白焼き | 枚(まい)・串(くし) |
状態ごとに正しい数え方を知ると、日本語の使い方にも深みが出てきます。
料理ごとの数え方を知って食を楽しもう
うなぎ料理にも、それぞれにふさわしい数え方があります。
う巻きや肝のようなアレンジ料理も、適切な数え方を知っておくことで、料理への理解が深まります。
| 料理名 | 数え方 |
|---|---|
| う巻き(丸ごと) | 本(ほん) |
| う巻き(切り分け) | 個(こ) |
| 肝(単体) | 個(こ) |
| 肝串 | 串(くし) |
正しい言葉を使って料理を楽しむと、味わいも会話も一段と豊かになります。