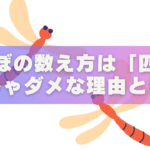2025年10月、メルカリの規約が大きく改定され、「事業者による個人アカウント利用」が正式に禁止となりました。
このニュースに戸惑った方も多いのではないでしょうか。
「もうメルカリで稼げない?」という不安の声もありますが、実はこの変化は、あなたのビジネスにとって新たなチャンスでもあります。
本記事では、改定の背景から「どこからが事業者なのか」、メルカリShopsとの違いやメリット・デメリット、そしてこれから生き残るための具体的な戦略までを徹底解説。
変化を恐れずに動き出すことで、むしろ今より稼ぎやすくなる可能性がある——そんな新しいルールの本質を、やさしく分かりやすくお伝えします。
メルカリの規約改定2025年版とは?

2025年10月、メルカリの利用規約が改定され、「事業者による個人アカウントの利用禁止」が正式に施行されました。
この変更は、これまでメルカリを副業や本業の販売チャネルとして使っていた多くの個人事業主にとって、大きなインパクトを与えました。
しかし、表面的な「規制強化」ではなく、長期的に見ると市場の健全化とビジネス環境の整備を意図したものです。
今回の改定で何が変わったのか
まず最も注目すべきポイントは、「個人アカウントを用いた事業活動の禁止」です。
これまでは、せどりや転売、ハンドメイド作品の販売なども、あくまで個人アカウントで可能でした。
しかし今回の改定によって、継続的に収益を得る販売者は、必ず「メルカリShops」への登録が求められるようになりました。
この動きの裏には、メルカリが個人間取引と事業取引を明確に区分し、トラブル防止と信頼性向上を図りたいという狙いがあります。
| 項目 | 旧ルール | 新ルール(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 出品アカウント | 個人・事業者ともに同一利用 | 事業者は「メルカリShops」のみ利用可能 |
| 対象者 | 誰でも利用可 | 継続的販売を行う事業者が対象 |
| 販売手数料 | 10% | 10%(変更なし) |
これにより、副業レベルでも反復継続的な販売をしている人は、個人アカウントでの出品が原則NGになります。
改定の背景と目的をわかりやすく解説
「なぜこのタイミングでルールが変わったのか?」と疑問に思う人も多いはず。
その答えは、メルカリが目指す市場の健全化と、消費者保護の強化にあります。
メルカリは元々、「家にあるいらないモノを手軽に売れる」CtoC(個人対個人)サービスとしてスタートしました。
ところが、近年では以下のような変化が見られていました。
- 業者が個人アカウントを使って毎日大量に出品
- 一般ユーザーの商品が埋もれて売れにくくなる
- トラブル発生時に、返品対応や保証が曖昧なまま放置される
こうした背景から、個人と事業者を明確に線引きし、それぞれに適切なルールと仕組みを提供する必要が生まれたのです。
| 課題 | 従来の問題点 |
|---|---|
| 出品の公平性 | 事業者が有利になり、個人ユーザーが不利に |
| トラブル時の対応 | 個人アカウントでは返品・返金の責任が曖昧 |
| 市場の透明性 | 実態が分からない業者が多数存在 |
このように、メルカリの規約改定は、ユーザーの利便性を守り、信頼されるマーケットプレイスを維持するための施策だといえます。
結果的に、誠実にビジネスを行う事業者にとっても、より安心して販売できる環境が整うことになります。
どこからが「事業者」になるのか?明確な判断基準

今回のメルカリ規約改定では、「事業者による個人アカウントの利用禁止」が打ち出されました。
ですが、ここで気になるのが、「自分はどこからが事業者になるの?」という点ですよね。
判断を誤ると、知らず知らずのうちに規約違反になるリスクもあるため、しっかりと理解しておく必要があります。
消費者庁ガイドラインによる目安
メルカリ自身は明確な「数値基準」を公表していません。
しかし、参考にすべきなのが「消費者庁」が公開している「通信販売における広告表示に関するガイドライン」です。
この中で「販売業者とみなされる可能性のある基準」が示されています。
| 判断基準 | 目安となる数値 |
|---|---|
| 出品点数 | 1か月に200点以上、または1度に100点以上 |
| 取引総額 | 過去1か月で100万円以上 |
| 継続性 | 仕入れ→販売を反復継続して行っている |
これらの条件に1つでも該当すれば、個人出品の枠を超えて「事業者」と判断される可能性があります。
あくまで目安ですが、メルカリの運営側もこの基準を参考に対応していると考えてよいでしょう。
あなたは対象?セルフチェックのポイント
では、自分の出品スタイルが「事業者」に該当するかどうかを判断するために、簡単なチェックリストを作成してみました。
- 毎月10点以上の商品を継続して出品している
- 商品を仕入れてから販売している(例:古着・新品の雑貨など)
- 月5万円以上の売上が安定してある
- 同じような商品を定期的に出品している
- 購入者とのやり取りに慣れていて、ビジネス感覚で対応している
このうち2つ以上当てはまる方は、「メルカリShops」への移行を前向きに検討すべきタイミングです。
「副業」はOK?「継続的な営利目的」かどうかがカギ
「私は副業だから大丈夫」「ちょっとした小遣い稼ぎだけど?」と思う方もいるかもしれません。
ですが、メルカリが問題視しているのは、「販売目的の継続性」と「営利性」です。
つまり、本業か副業かではなく、利益を得るために継続的に売っているかどうかがポイントになります。
一例をあげると…
| 販売スタイル | 判断されやすさ |
|---|---|
| 自宅の不用品をたまに出品 | 個人利用と判断されやすい |
| 古着を仕入れて毎月販売 | 事業者と判断される可能性大 |
| ハンドメイドを月5回以上出品 | 反復性がある=事業性あり |
このように、出品スタイルによって評価は大きく変わります。
特に「在庫を抱えている」「売上管理をしている」「リピーターがいる」などの状態は、事業活動の特徴そのものです。
「副業だから安心」と思い込まず、今一度、自分の出品内容を棚卸ししてみましょう。
なぜ個人アカウントでの販売が制限されたのか

「どうして今、事業者の個人アカウント利用が禁止されたの?」という疑問は、多くの出品者が感じていることです。
その背景には、メルカリというプラットフォームが直面していた“静かなひずみ”の蓄積がありました。
この章では、その理由を「ユーザー体験の悪化」「トラブル増加」「信頼性の低下」の3つの視点から、深掘りして解説します。
個人ユーザーの不満と市場の歪み
メルカリはもともと、個人が不要になったモノを手軽に売買できる「フリマアプリ」として人気を集めました。
しかしここ数年で、事業者が在庫商品を毎日出品するような「ビジネス利用」が急増。
その結果、次のような問題が起きていました。
| 課題 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 検索結果の偏り | 一般ユーザーの商品が埋もれてしまう |
| 価格競争の激化 | 個人出品者が価格で勝てなくなる |
| 出品体験の格差 | 趣味出品者が売れずに離脱する |
このように、本来の「個人が楽しむフリマ」という土台が揺らいでいたのです。
結果的に、メルカリ全体のユーザー体験がじわじわと悪化していきました。
増加するトラブルと、曖昧な責任の所在
もうひとつの問題は、トラブル時の対応があいまいだった点です。
たとえば、事業者が個人アカウントを使って販売していると、こんな状況が起こり得ます。
- 初期不良品への対応が曖昧
- 返品を受け付けないという一方的な姿勢
- 購入者から「ショップじゃないの?」という混乱が発生
通常、ECモールでは「販売業者=返品・保証などの法的責任を負う立場」とされます。
しかし個人アカウントを装った事業者の場合、トラブルが起きたときのルールが適用されず、購入者が泣き寝入りするケースもあったのです。
メルカリとしても、こうした曖昧な取引を放置しておくと、プラットフォーム全体の信頼を失うリスクが高まると判断したわけです。
なぜ「今」このルール変更が必要だったのか
「問題があったなら、もっと前に変えるべきだったのでは?」と思う方もいるかもしれません。
実はメルカリはここ数年、じわじわとビジネス利用に関する取り締まりを強化してきました。
今回の改定は、その最終的なルールの明文化といえます。
背景には以下のような社会的変化もあります。
| 社会の変化 | 影響 |
|---|---|
| 副業の一般化 | 販売を通じて収益を得る個人が増加 |
| 税務署の監視強化 | 所得報告の義務が強まる |
| 消費者保護の強化 | 販売者の責任明確化が必要に |
つまり、これまでグレーゾーンだった部分に、きちんと「線引き」をするタイミングが来たということです。
「個人はフリマ」「事業者はショップ」への転換
今回の規約改定を一言でまとめるなら、「利用目的に合わせた正しい場所を使いましょう」というメッセージです。
個人であれば、これまで通り気軽にフリマとして利用可能。
一方、継続的に販売をしている人は、きちんとショップ運営者としての自覚と仕組みを持つべき、というわけですね。
この線引きによって、次のようなメリットが期待されます。
- 購入者が安心して買い物できる
- 出品者もルールに沿って堂々と販売できる
- メルカリ全体の信頼性が高まる
つまり、規約改定は「締め出し」ではなく、「健全に売り続けるための進化」なのです。
メルカリShopsとは?個人アカウントとの違いを比較

「メルカリShopsってよく聞くけど、結局どんな仕組みなの?」という疑問を持つ方も多いと思います。
この章では、メルカリShopsの全体像と個人アカウントとの違いを、具体的な機能・仕組み・活用シーンを交えて詳しく解説します。
あなたの販売スタイルがどちらに適しているかを判断するためにも、この違いをしっかり押さえておきましょう。
メルカリShopsは「事業者向けメルカリ」
メルカリShopsは、メルカリ内にある「ネットショップ開設機能」です。
見た目は通常のメルカリとほとんど同じですが、出品者が“店舗名”を持ち、商品も“ショップからの販売”という形で提供される点が大きく異なります。
つまり、同じアプリ内にいながら、「個人のフリマ」と「ビジネス用のEC」の2つの顔を持っているということです。
メルカリShopsは、以下のような販売者に向いています。
- 仕入れや製造を行い、継続的に販売している
- 在庫を複数管理し、同じ商品を何度も出品する
- 自社ブランドや屋号を持っている、あるいは作りたい
機能・仕組みの違いを表で徹底比較
個人アカウントとメルカリShopsでは、利用者の目的に合わせて機能やサポートが大きく異なります。
次の表でその違いを整理してみましょう。
| 比較項目 | 個人アカウント | メルカリShops |
|---|---|---|
| 出品対象 | 不用品、中古品 | 新品商品、仕入れ品、自社製品 |
| 販売スタイル | 単発的、気まぐれ | 継続的、事業としての販売 |
| 在庫管理 | 1商品1在庫 | サイズ・色ごとに複数在庫管理が可能 |
| スタッフ運営 | 不可 | 複数人でのアカウント運用が可能 |
| ショップページ | なし | ショップ名、ロゴ、レビューなどで差別化 |
| 配送 | メルカリ便のみ | クールメルカリ便など事業向け配送も対応 |
| 分析機能 | 簡易な販売履歴 | 売上・アクセス数・商品ごとの分析が可能 |
| 審査 | 不要 | 事前審査・事業者情報の提出が必要 |
特に在庫管理や販売分析など、「売上を伸ばすための仕組み」が充実している点は大きな差別化ポイントです。
「販売場所」ではなく「育てる店」へと変わる感覚
個人メルカリでは、1つの商品を出して、売れたら終わりという感覚が一般的でした。
しかし、メルカリShopsは「お店を運営する」という意識が求められます。
つまり、ただモノを売るのではなく、“信頼される店づくり”を目指すことが重要になります。
たとえば、以下のような工夫が求められます。
- アイコンやロゴを統一してブランド感を出す
- 商品説明を丁寧に整えて、世界観を作る
- レビュー対応を丁寧に行い、リピーターを増やす
このように、メルカリShopsは「単なる出品」から「本格的なショップ運営」へとステージが変わる場所なのです。
手数料・費用面での安心感も魅力
メルカリShopsへの移行を考える上で気になるのが、「コストが増えるのでは?」という不安ですよね。
結論から言うと、販売手数料や振込手数料は個人アカウントとまったく同じなので、追加のコストはかかりません。
| 費用項目 | 個人アカウント | メルカリShops |
|---|---|---|
| 販売手数料 | 10% | 10% |
| 入金手数料 | 200円/回 | 200円/回 |
| 登録費用 | なし | なし |
| 月額利用料 | なし | なし |
それでいて、分析ツール・在庫管理・ブランド構築などの“ECモール級の機能”が無料で使えるというのは大きな魅力です。
つまり、コストをかけずに本格的なショップ運営ができるのが、メルカリShops最大の強みといえるでしょう。
メルカリShopsのメリット・デメリットを総点検

メルカリShopsは、ただの「事業者向け出品窓口」ではありません。
本気で売上を伸ばしたい人にとっては、マーケティング・効率化・顧客管理を一手に担える“ビジネス基盤”とも言える存在です。
ここでは、Shopsが提供する機能の真価と、注意すべきリアルな課題の両方を深掘りしてお伝えします。
在庫管理・分析・API連携:機能面のメリットは段違い
まず特筆すべきは、メルカリShopsに実装されている“売れるための仕組み”です。
これは、単なる出品機能にとどまらず、「効率よく」「計画的に」「長期的に」売るための設計が施されています。
| 機能 | 特徴 | 活用メリット |
|---|---|---|
| 在庫バリエーション管理 | 1商品ページにサイズや色をまとめて登録可能 | 在庫の管理がラクになり、見やすさ・買いやすさが向上 |
| 販売データ分析 | 商品ごとのアクセス数・売上・転換率を可視化 | どの商品が伸びてるか、どこを改善すべきか一目で分かる |
| API連携 | 他のECモールや在庫管理ツールと自動連携 | 出品・在庫更新・注文処理の手間を大幅カット |
| スタッフアカウント | 複数人で役割分担(例:梱包・顧客対応) | 副業でも無理なく運営でき、チーム販売も可能 |
これらは「フリマアプリ」としてのメルカリでは提供されていなかった、ECサイト並みの事業機能です。
特に分析と在庫管理が強化されることで、「なんとなく売っている状態」から脱却できるのが最大のメリットです。
販売者・購入者どちらにもメリットがある構造
Shopsの優れている点は、出品者だけでなく「購入者側の体験」にも良い変化をもたらしていることです。
- 商品ページが見やすくなり、まとめ買いがしやすい
- 「ショップ単位」での検索ができ、リピーターが増えやすい
- 明確な販売責任があるため、トラブル対応も安心
顧客にとって「信頼できる店から買う」という安心感が加わることで、リピート率が上がるのは、個人アカウントにはない強みです。
準備と運用におけるリアルな課題と対応策
一方で、Shopsに移行するときにつまずきやすいポイントもあります。
特に「副業や趣味レベルで販売していた人」にとっては、最初の準備が大変に感じるかもしれません。
| 課題 | 詳細 | 解決のヒント |
|---|---|---|
| 出店審査 | 本人確認・事業内容の入力・口座登録が必要 | 事前に用意すべき情報をメモしておくとスムーズ |
| 商品登録の手間 | 画像・説明・バリエーション設定など入力項目が多い | テンプレートを活用して一括編集を進めると時短に |
| ブランディングの必要性 | ロゴ・ショップ名・見せ方の整備が必要 | 無料のデザインツール(Canvaなど)を活用する |
| レビューの初期ゼロ状態 | 新規ショップでは信頼が得づらい | 購入特典や丁寧なメッセージ対応で初期評価を獲得 |
とはいえ、これらの課題は「慣れればすべて日常業務として回せるレベル」です。
最初の壁を越えるかどうかが、“稼げるショップ運営者”への分かれ道だといえるでしょう。
Shopsを使うべき人/使わなくていい人の境界線
では、全員がメルカリShopsを使うべきなのでしょうか?
答えはNOです。以下のように、「販売目的の明確さ」で判断するのがポイントです。
| 出品スタイル | おすすめの運用方法 |
|---|---|
| 単発の不用品出品 | 個人アカウントで十分 |
| 仕入れ商品を複数出品 | Shops運用が必須 |
| 同じ作品を毎月販売(ハンドメイドなど) | Shopsに切り替えた方が有利 |
| 副業で毎月売上がある | 早めにShopsでの土台構築を |
継続的に販売しているなら、個人のままで居続けるリスクの方が高くなることを覚えておきましょう。
「もう稼げない?」は誤解!これからの販売戦略

「メルカリの規約が厳しくなった=もう稼げない」と感じている方、それは大きな誤解です。
実はこのタイミングこそが、販売スタイルを進化させて“安定して稼ぐ”ステージへ移行するチャンスなんです。
この章では、メルカリでこれからも稼ぎ続けるために必要な“3つの戦略軸”を中心に解説していきます。
なぜ「終わり」ではなく「始まり」なのか
一部の出品者からは、「せどりできなくなった」「ハンドメイドが規制された」といった声も聞かれます。
しかし、事実としては販売が禁止されたわけではなく、「場所が変わった」だけ。
むしろ、メルカリShopsによって以下のような“好転”が始まっています。
| 項目 | 規約改定前 | メルカリShops移行後 |
|---|---|---|
| 販売の自由度 | 仕入れや数量に制限なし(だがグレー) | 安心して継続販売ができる |
| 顧客管理 | アカウント単位でしか対応不可 | レビュー・フォロワー・メッセージで関係性を構築 |
| 成長性 | 限界がある | 在庫・分析・ブランド力でスケール可能 |
つまり、ルールが整ったからこそ“堂々とビジネスができる”時代に突入したとも言えます。
「継続性・営利性」が戦略のカギ
規約改定の根幹は、「不用品を売る場」と「商売をする場」を分けることでした。
この線引きを理解すれば、自分の販売スタイルにあった戦略が立てやすくなります。
- 月に1回しか出品しない → フリマでOK
- 毎月仕入れて売っている → Shopsに移行
- 口コミやリピーターを育てたい → Shopsが有利
これを機に、「自分は何を目指しているのか?」を明確にすることが成功の第一歩になります。
これからの3本柱:「効率化・差別化・ブランド化」
今後の販売で成果を上げるために、最も重要なキーワードはこの3つ。
ただ出すだけの時代は終わり、“お店としてどう見られるか”が問われるようになってきました。
| 戦略 | 具体例 | 狙える効果 |
|---|---|---|
| 効率化 | API連携、在庫自動化、テンプレート作成 | 作業時間削減+売上機会の最大化 |
| 差別化 | 写真の工夫、商品名のSEO、購入特典の提供 | 価格競争に巻き込まれずに選ばれる |
| ブランド化 | ロゴ・ショップ名の統一、SNS連携、レビュー管理 | リピーター獲得+価格以外の価値で勝負 |
この3つを同時に育てていくことで、Shopsは「単なる販売チャネル」から“収益を支えるビジネス資産”になります。
短期利益ではなく“信頼の積み重ね”がカギ
これからの時代、メルカリで稼ぎ続けるには「1回売って終わり」ではなく、「何度も買ってもらえる」環境を作ることが重要です。
それには、次のような意識改革が欠かせません。
- 売上よりもレビュー評価を重視する
- 商品のクオリティだけでなく、体験価値を届ける
- 価格よりも“誰から買うか”を選ばれる存在になる
これまで個人アカウントでは不可能だった「信頼の蓄積」が、Shopsでは実現できるようになったのです。
この違いを活かせる人こそが、今後のメルカリで安定して稼ぎ続けられる存在になります。
小規模事業者がメルカリで生き残るために

「1人で運営」「副業で片手間」「予算に限りがある」——そんな小規模事業者こそ、メルカリShopsという舞台で真価を発揮できます。
なぜなら、Shopsは“最小の労力で最大の効果を出す仕組み”が整っているからです。
この章では、限られたリソースでも成果を出せる「戦略思考」と「実践ノウハウ」を、さらに深く掘り下げてご紹介します。
効率化:仕組みで売上を最大化する考え方
時間も人手もない小規模事業者にとって、最も重要なのは「繰り返し作業を自動化・標準化すること」です。
Shopsには、そのための仕組みが揃っています。
| 機能 | 効率化ポイント | 活用例 |
|---|---|---|
| テンプレート登録 | 説明文・配送設定などを雛形にできる | 出品作業を毎回ゼロから作らなくてよい |
| API連携 | 他のECモールや管理ツールと接続 | 在庫数や商品情報の一括反映が可能 |
| スタッフ権限 | 作業を分担できる | 家族やアルバイトに発送業務だけ任せる |
大事なのは「自分の手を動かさなくても回る仕組み」を早い段階で構築することです。
副業・子育て中・本業が忙しい人ほど、まず“仕組みづくり”に時間を投資するべきです。
差別化:「自分を選んでもらう」ための具体施策
メルカリには、同じ商品を売っている出品者がたくさんいます。
だからこそ、「誰から買うか」が選ばれる時代です。
特にShopsでは、以下のような差別化が可能です。
- 写真の統一:背景色をそろえるだけで「プロ感」が出る
- 商品名の工夫:「【送料無料】選べる5色」など、検索ワードを自然に含める
- ストーリー性の追加:「この商品が生まれたきっかけ」「こだわりの素材」などを記載
差別化とは、価格やスペックではなく、感情や信頼で選ばれるようにすることです。
大量販売ではなく“刺さる相手に届ける”視点が、小規模事業者には必要です。
ブランド化:記憶に残り、繰り返し買われる店になる
Shopsの最大の強みは、「ショップ」という形で“顔のある販売”ができることです。
これはつまり、リピート・口コミ・ファンづくりに直結します。
| ブランド構築の要素 | 効果 | 具体施策 |
|---|---|---|
| ショップ名の一貫性 | 覚えてもらいやすくなる | ジャンル+名前(例:古着のまるやま)など |
| ロゴ・アイコン | 印象を固定できる | Canvaなどで無料作成し、SNSでも統一 |
| レビュー管理 | 信頼と安心感の構築 | お礼メッセージ+丁寧な対応で高評価を獲得 |
| SNS連携 | 接触頻度を増やす | InstagramやX(旧Twitter)で新商品や制作裏話を発信 |
「また買いたい」と思われるには、売る以上に“覚えてもらう工夫”が必要です。
これができると、価格競争に巻き込まれず、長期的に安定した売上をつくることができます。
「1人でもできる」を「1人だからこそできる」へ
小規模事業者が強くなれる理由は、「身軽であること」「顧客と近いこと」「自由に変化できること」です。
大手にはない個人の強みを活かせば、十分に戦えます。
- ✅ 顧客に名前で覚えてもらえる
- ✅ ニッチな商品でも柔軟に対応できる
- ✅ メール1通でファンと深くつながれる
大きくなろうとしすぎず、小さいからこその強みを徹底的に磨く。
それこそが、メルカリで長く稼ぎ続ける最短ルートです。
まとめ:規約改定で何が変わり、どう対応すべきか

2025年10月のメルカリ規約改定は、多くの出品者にとって「転機」となる出来事でした。
けれども、それは決して「終わり」ではなく、“これからのメルカリで本気で稼ぐ人”と“趣味で使う人”を分ける明確なルールができただけなのです。
ここでは改めて、今回の改定で見えてきた本質と、これから取るべきアクションを整理しておきましょう。
規約改定の本当の意味とは?
今回の変更を、「規制強化」や「自由の制限」として受け止めてしまうのはもったいない話です。
メルカリが目指しているのは、個人が安心してフリマを楽しめる環境と、事業者がビジネスとして育てられる土台を両立させることです。
| 目的 | 具体的な施策 |
|---|---|
| 個人の保護 | 事業者が個人アカウントを使うことを禁止 |
| 事業者の成長支援 | メルカリShopsにビジネス向け機能を集約 |
| プラットフォーム全体の健全化 | 責任の所在を明確にし、取引トラブルを減らす |
つまり、規約改定は「抑制」ではなく「整備」なのです。
そして、この整備に最も早く適応できた人こそが、これからのメルカリ市場で大きく伸びる可能性を持っています。
改定によって変わったこと・変わらないこと
| 項目 | 改定によって変わったこと | 変わらないこと |
|---|---|---|
| 販売アカウント | 事業者はShops必須に | 個人は引き続き気軽に出品OK |
| 手数料 | 変更なし(10%) | 同じコストでShopsの機能が使える |
| 出品ルール | 販売継続・仕入れがある場合は事業扱い | 単発出品は規制対象外 |
| 対応責任 | 事業者には返品・品質保証などの責任が発生 | 個人間取引の基本ルールは継続 |
ポイントは、「取り組み方」が変わっただけで、「チャンスの大きさ」は変わっていないということです。
これから取るべきアクション:3つのチェック
では、今この記事を読んでいるあなたが今後もメルカリで成果を出していくには、何から始めるべきでしょうか?
以下の3点をチェックし、すぐに動き出す準備を整えましょう。
| チェックポイント | 対応内容 |
|---|---|
| ① 自分の販売スタイルを明確にする | 継続的か単発か?営利目的か?を自己診断 |
| ② Shops移行を視野に入れる | 当てはまるなら早めに審査申請して準備開始 |
| ③ “店”としての運営に切り替える | ロゴ・レビュー・SNSなどの整備を始める |
特に③は、「売れるかどうか」ではなく、「覚えてもらえるかどうか」に直結します。
メルカリShopsは、単なる出品場所ではなく、“あなたというブランドを育てる場”なのです。
変化に適応できる人が最後に残る
メルカリの環境が変わっても、求められる本質は変わりません。
それは、「誠実に、丁寧に、必要な人に届ける」という姿勢です。
- ✅ 規約に振り回されず、正しく活用できるか?
- ✅ 規制を逆に“差別化のチャンス”と捉えられるか?
- ✅ 変化を受け入れ、柔軟に対応できるか?
その視点さえあれば、今回の規約改定はむしろ“追い風”になるはずです。
今こそ、自分の販売を「趣味」から「事業」へ、本気でステージアップさせる時です。