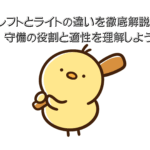突然、スマートフォンに表示された「+999」という見慣れない番号──その瞬間、あなたは戸惑いや不安を感じたかもしれません。 「誰から?」「どこの国?」と疑問が浮かび、もしかすると、折り返すべきか悩んだ人もいるでしょう。
この番号は、通常の国際電話では考えにくい存在しない国番号であり、詐欺や迷惑電話といったリスクを孕んでいるケースが非常に多いのです。
本記事では、そんな「+999」の正体や仕組み、そして絶対に知っておくべき安全な対処法について、専門的な視点と実例を交えながら徹底的に解説していきます。
「知らない番号=怖いもの」と思い込まず、正しい知識で冷静に対応するための一歩として、ぜひ最後までお読みください。
本当にあった怖い電話番号「+999」の実態とは?

日々の生活の中で突然スマートフォンに表示される「+999」という番号に、驚きや不安を感じた経験はありませんか?実際に、「これはどこの国の番号なのか?」「もしかして大切な連絡?」と、つい気になってしまう人は多いものです。しかしこの番号、結論から言えば「実在しない」番号です。
+999という番号は、国際電話の規格上、実在する国や地域には割り当てられていません。これは、国際電気通信連合(ITU)が定める国番号一覧にも掲載されておらず、正規の通信手段としては使用されない番号です。
にもかかわらず、この番号が着信履歴に表示される理由の多くは、「スプーフィング」と呼ばれる技術に起因します。これは、発信者が任意の番号を設定して相手に表示させる手法で、悪意のある発信者が、自分の電話番号を隠すためや、受け手の注意を引くために使用することが多いです。
実際、警察庁や総務省、そして各通信キャリアの公式情報でも、「+999」のような存在しない番号からの着信は、詐欺や迷惑電話の可能性があるため注意すべきと警告されています。
例えば、詐欺グループが「重要なお知らせがあります」などの内容でSMSを送りつけたり、通話を通じてクレジットカード情報や個人情報を盗み出そうとするケースが多数報告されています。
「+999」からの着信があった場合、最も安全な行動は「無視すること」です。折り返し電話をかける必要もありませんし、もし出てしまってもすぐに通話を終了すれば大きな問題にはなりません。
また、端末側で着信拒否の設定を行ったり、迷惑電話ブロックアプリを活用することで、今後の着信を未然に防ぐことができます。
重要なのは、「+999という番号は、正規の国番号ではなく、詐欺や迷惑行為の疑いが極めて高い」という事実を知り、冷静に対応することです。特に高齢者やスマホ操作に慣れていない方は、不安を感じたら一人で抱え込まず、家族や専門機関に相談するようにしましょう。
実は国際番号ではない「+999」
「+999」は、一見すると国際電話の発信元のように思えますが、実は世界中どこの国にも正式に割り当てられていない“架空の国番号”です。国際電気通信連合(ITU)が公表している国番号一覧にも「+999」という番号は存在せず、これが着信履歴に表示されるのは通常の通信ルートを経ていない“特殊な仕組み”によるものです。
このような番号が表示される背景には、発信者番号を意図的に偽装する「スプーフィング(Spoofing)」という技術が関係しています。これは、VoIPやPBXを使った通信で、送信側の番号を偽って表示させる技術であり、詐欺業者などがしばしば利用しています。
なぜ表示されるのか?その背景に迫る
なぜ、あえて「+999」のような存在しない番号を使うのでしょうか?理由の一つは“注目を集めるため”です。見慣れない番号は心理的な警戒感を生むと同時に、「誰だろう?」という興味も引き出します。この心理を突いて、詐欺グループは受信者に折り返しを促したり、SMSのリンクをタップさせたりしようとします。
また、通信システム側のエラーやテスト中の通話、非通知設定の影響で+999が表示されてしまうケースも報告されています。どちらにしても、発信元の実体が不明であることには変わりなく、信頼できない番号であることは間違いありません。
警察や行政の公式見解は?
警察庁、総務省、主要キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク等)は、公式に「+999」などの不明国際番号からの着信について警鐘を鳴らしています。特に、折り返し通話によって高額通話料を請求されたり、個人情報を聞き出されたという報告があり、注意喚起が行われています。
警察の相談窓口「#9110」や、消費者庁の「188(消費者ホットライン)」でもこうした不審な電話に関する相談が増えており、必要であれば速やかに連絡を取るべきです。
また、各キャリアの公式サイトでは「迷惑電話対策ページ」が設けられており、着信拒否の方法や、通話記録の確認方法なども詳しく案内されています。困ったときは、まず公式情報をチェックするのが安心・確実です。
+999=どこの国?実在しない番号の謎

+999という番号は、国際的な電話番号体系において“正式には存在しない”番号です。これは国際電気通信連合(ITU)が定める国コードに含まれておらず、現時点では世界のどの国にもこの番号は割り当てられていません。
つまり、+999は「誰かが意図的に表示させた番号」である可能性が極めて高く、自然発生的なものではありません。もし、この番号から着信があった場合、それはほとんどの場合で「偽装された発信者情報」だと見てよいでしょう。
技術的な観点から言えば、このような番号は主にIP電話やコールセンターシステムで使われる「番号スプーフィング」によって表示されるものです。
スプーフィングとは何か?偽装技術の仕組み
スプーフィング(Spoofing)とは、発信者が実際の電話番号とは異なる番号を“偽装”して着信側に表示させる技術です。
たとえば、本来なら+1(アメリカ)や+81(日本)などの番号が表示されるはずの通話が、+999という存在しない番号で着信するように改ざんされることがあります。
このような手口は、VoIP(インターネット電話)やPBX(構内交換機)の設定を悪用することで比較的簡単に行われ、詐欺電話、なりすまし、迷惑電話の一環として用いられます。
スプーフィングを使う目的は主に以下の3つです:
- 発信者の実態を隠す(匿名化)
- 正規の番号に見せかけて信頼させる(なりすまし)
- 受信者を混乱させ、不安を煽る(心理誘導)
この技術自体は正規のコールセンターなどでも使われていますが、悪意を持った利用者が使うことで、詐欺や情報搾取のリスクが急増しています。
つまり、「+999」という番号は、それだけで“危険信号”と捉えて問題ないのです。
なぜ「+999」を表示するのか?代表的な詐欺手口

+999からの着信には、いくつかの“明確な目的”が隠されています。それは受信者に対して恐怖心や緊急性を与え、折り返し通話やリンククリックといった「具体的なアクション」を引き出すためです。
詐欺グループは、相手を騙すために緻密な仕掛けを施してきます。ここでは、よく使われる3つの典型的な詐欺手口を紹介します。
ワン切りで折り返させる古典的な詐欺
これは「ワン切り詐欺」と呼ばれる手口で、+999からの着信が1コールで切れる、もしくは出る前に切れるのが特徴です。これによって「急ぎの用件かもしれない」と思った受信者が、折り返し電話をかけると、高額な通話料が発生する仕組みになっています。
この通話料の一部が、詐欺業者に還元されるように設定された「プレミアム通話番号」が使われており、たった数十秒の通話で数千円の請求が来ることも。海外からの国際料金が発生する可能性もあるため、絶対に折り返してはいけません。
実在企業を装ったSMSによる誘導
着信と同時に届くSMSや、その後に送られてくるメッセージも要注意です。「Amazon」「佐川急便」「銀行」など、実在する有名企業を装って、個人情報を入力させるフィッシングサイトへと誘導する内容が増加しています。
メッセージ内には「不在連絡です」「アカウントに異常があります」などの一見それらしい文言が並び、URLが記載されていることが多いです。しかし、これらのリンクは100%クリック厳禁。アクセスしただけでマルウェアに感染する危険性もあります。
偽サイトへと誘う巧妙なフィッシング詐欺
さらに進化した詐欺では、スマートフォンの画面に表示されるWebサイトが本物と区別がつかないほど精巧に作られており、入力欄も正規サイトとほとんど同じ見た目になっています。
たとえば、ログイン情報やクレジットカード番号、SMS認証コードなどを入力させることで、不正ログインや不正送金につながるケースが多発しています。
怪しい番号の共通点とは
+999のような怪しい番号に共通して言えるのは、以下の特徴です:
- 着信時刻が深夜・早朝などの違和感ある時間帯
- 着信後すぐに切れる(ワン切り)
- 繰り返し着信がある(緊急性を演出)
- 留守電が残っていない(会話を避けるため)
これらの特徴を備えた番号からの着信は、すべて「怪しいもの」として認識し、冷静に無視・拒否設定をすることが最善です。
なぜこんな番号からかかってくる?4つの背景

「+999」という異常な番号が着信に表示される背景には、いくつかの技術的・詐欺的な要因が存在しています。ただのイタズラや偶然ではなく、ほとんどの場合、システム的な仕組みや悪意のある操作によるものです。
ここでは、その代表的な4つの理由について詳しく見ていきましょう。
① 通信会社やシステム上の番号
一部の通信会社では、システムの保守や動作確認の際、仮の番号として「+999」などの番号が表示されるケースがあります。これは本来、一般ユーザーには見えないように設計されているものですが、設定ミスや仕様の不具合により表示されてしまうことがあります。
たとえば、通信ネットワークを切り替える際や、ネットワーク障害の調査などで使われる“内部通話”で、こうした仮番号が使用されることがあるのです。
② 迷惑電話・詐欺の可能性
最も多いのがこちら。+999という番号をわざと表示させ、ユーザーを混乱させることで、折り返し通話や情報入力を誘導する「詐欺的な意図を持った着信」です。
これは、先に解説したスプーフィング技術と組み合わされることで、あたかも“存在する正規の発信元”のように装うことも可能です。最近では、音声ガイダンスによって個人情報を入力させる詐欺や、架空請求などもこの番号が使われています。
③ 発信者情報の偽装(スプーフィング)
スプーフィングとは、意図的に発信番号を偽装して、他人や架空の番号を表示させる手法です。+999のような見慣れない番号は、こうした偽装番号としてしばしば選ばれます。
この手口の厄介なところは、見た目だけでは「誰がかけてきたのか」判断できないという点です。さらに、+999のように明らかに怪しい番号を使うことで、逆に「気を引いて」アクションを起こさせようとする意図があることも。
④ 間違い電話やテスト用番号
極めてまれなケースですが、間違って設定されたテスト用端末や、海外で使用されている特殊な通信システムの影響で、+999が誤って発信元として表示されることもあります。
特に国際ローミング中の設定ミスや、企業が使用するIP電話システムの誤作動によって、不自然な番号が表示される事例が報告されています。
いずれにしても、+999という番号は「通常ではあり得ない表示」であることに変わりなく、正体が分からない番号には慎重な対応が求められます。
着信で課金されることはある?料金の仕組み

+999という番号からの着信があると、多くの人が真っ先に気になるのが「料金は発生するのか?」という点です。特に海外番号が絡むと、「着信しただけで通話料がかかるのでは?」と不安になるのも当然です。
ここでは、着信に関する料金の仕組みや注意点について、わかりやすく解説します。
着信だけでお金がかかることはない
まず結論から言えば、「着信を受けただけで通話料金が発生することは基本的にありません」。国内でも国際でも同様で、着信者が料金を負担するケースは非常にまれです。
日本の通信キャリアでは、着信通話は原則として無料に設定されており、着信時にお金を請求されることはありません。したがって、+999からの着信があっても、電話に出ない限り、あるいは応答しても通話が成立しない限り、料金がかかることはほぼないのです。
折り返し・SMS返信の落とし穴
しかし、問題は「折り返した場合」です。先ほど紹介した「ワン切り詐欺」などでは、ユーザーが不安に駆られて折り返すことで、悪質な高額通話番号に誘導されてしまいます。
この場合、国際電話料金に加えて、特別なプレミアム通話料金が上乗せされ、数千円から数万円規模の請求が発生することがあります。また、SMSに返信した際も、メッセージを通じてマルウェアに感染するリスクや、位置情報などの個人情報が取得される危険性も否定できません。
絶対避けたいNG行動とは?
+999からの着信に対して、次のような行動は絶対に避けてください:
- 知らない番号に不用意に折り返し電話をかける
- SMSのURLをクリックする
- 「詳細はこちら」「認証コード入力」などの文言に従って操作する
- 相手が名乗っても、個人情報や口座情報を話す
これらの行為は、詐欺グループの思うツボであり、被害につながる可能性が非常に高いです。
安全にスマートフォンを利用するためには、「知らない番号には出ない・返信しない・調べてから対応する」という3原則を徹底することが何より重要です。
話してしまった・個人情報を渡したら?

「知らずに出てしまった…」「うっかり名前や電話番号を答えてしまった…」 そうした場合でも、慌てず冷静に対処することが重要です。ここでは、話してしまった後に取るべき具体的な行動と、被害を最小限に抑えるための対処法を紹介します。
通話した場合の対処フロー
- 通話をすぐに終了する: 相手が不審な内容を話し始めた時点で、会話を中断し、即座に電話を切りましょう。
- 通話履歴を記録する: 着信日時や通話時間、相手の言動などをメモしておくと、後から相談する際に役立ちます。
- 着信拒否・ブロック設定を行う: その番号からの今後の着信を防止するため、端末でブロック設定を行いましょう。
- 通話録音があれば保存する: 録音が可能なアプリを使用していた場合、証拠として保存しておくと有効です。
情報を伝えてしまったときの対応策
万が一、以下のような情報を伝えてしまった場合は、迅速に対応する必要があります:
- クレジットカード情報 → すぐにカード会社へ連絡し、利用停止または再発行手続きを依頼。
- 銀行口座情報 → 銀行へ連絡し、不正送金を防ぐための対策を相談。
- 電話番号・名前・住所 → これだけでは直接被害は出にくいが、なりすましや勧誘被害の温床になる可能性があるため注意。
- SMS認証コード → 二段階認証が突破された恐れがあるため、対象サービスのパスワード変更・ログイン履歴確認を。
不安な場合はここに相談を
一人で悩むのは禁物です。以下の専門窓口に相談することで、より適切なアドバイスを受けることができます。
- 警察相談専用電話「#9110」:緊急性のない不審な電話について相談可能。
- 消費者ホットライン「188」:詐欺被害や悪質商法に関する相談。
- 通信キャリアのカスタマーサポート:着信履歴の確認や迷惑電話対策のアドバイス。
これらの窓口は、あなたの不安や疑問を解消するために設けられた重要な支援リソースです。迷ったらまず相談することが、被害を防ぐ最善策となります。
掛け直しても繋がらない?その理由とは

「+999から着信があったので、試しに掛け直してみたけど、繋がらなかった」──これは非常によくあるケースです。
では、なぜ+999には掛け直しても繋がらないのでしょうか? その理由は、技術的・制度的にいくつかの要素が絡み合っています。
存在しない番号だから繋がらない
まず前提として、「+999」は実在する国や地域の電話番号ではありません。国際電気通信連合(ITU)によって正式に割り当てられていないため、この番号自体が通信網の中で“有効なエンドポイント”として機能していないのです。
つまり、+999に対して通話を発信しても、宛先が見つからずに「この電話番号は使われておりません」といったアナウンスが流れるか、そもそも発信すらできない構造になっています。
スプーフィングで偽装された番号の可能性
詐欺業者が使用するスプーフィング技術では、実際の発信元とは異なる番号を画面に表示させることができます。この場合、着信の発信元は実際には全く別の電話番号で、表示された+999は“偽装された仮番号”に過ぎません。
したがって、折り返しをかけたところで、表示されていた番号と実際の発信元が一致しないため、通話が成立しないという現象が発生します。
自動応答システムやロボコールの影響
+999からの着信の多くは、ロボットによって自動で発信されている「ロボコール(自動通話)」です。この場合、発信側には受信応答の仕組みがそもそも存在せず、掛け直しても何も応答しないか、通話が拒否されるように設定されています。
このような仕組みは、詐欺グループが“受け身”で個人情報を取得するのではなく、能動的に相手の反応を確認したり、通話成立時にだけスクリプトを実行するために用いられています。
掛け直す意味がない理由まとめ
- 実在しない番号である(通信ルートが存在しない)
- 偽装表示であるため、実際の発信者に届かない
- 自動発信のため、受信側に通話対応機能がない
これらの理由により、「+999に折り返すこと自体に意味がない」ことは明白です。万一折り返しても通話料金が発生する可能性があり、リスクだけが高まるため、絶対に掛け直さないようにしましょう。
【まとめ】+999からの着信にどう対応すべきか?

+999という番号は、一般的な国際番号とは異なる“存在しない番号”であり、そこには詐欺や不正アクセスといったリスクが潜んでいます。本記事で紹介した内容をもとに、以下のポイントをしっかり押さえて対応するようにしましょう。
✔ 覚えておきたい対応ポイント
- +999は実在しない番号であり、基本的に危険な着信である
- 通話を受けただけで料金が発生することはないが、折り返しはNG
- スプーフィングによる番号偽装の可能性が高い
- 個人情報を話した・入力した場合は速やかに対応・相談を
- 不審な着信は迷惑電話ブロック機能や通報を活用する
✔ 安心のための3原則
- 出ない(見知らぬ番号は無視)
- 掛け直さない(興味本位でもNG)
- 調べる(番号を検索して確認)
特に高齢者やスマートフォンに不慣れな方は、家族で情報を共有し、「怪しい番号はすぐに相談できる」体制を整えておくことが重要です。
知らない番号に出るのが怖い時代だからこそ、冷静な判断と正しい知識が、あなたと大切な人の安全を守る最大の武器になります。
ぜひこの情報を周囲にもシェアし、詐欺被害ゼロの社会を目指していきましょう。